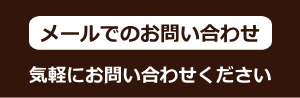兵庫県産材を使用した 中規模木造建築物 事例紹介 兵庫県立総合射撃場 管理棟
概要
兵庫県の木のセミナーで訪れた 兵庫県産材を使用した 中規模木造建築物の事例を紹介します。兵庫県立総合射撃場は、昨今の動物被害が与える影響を苦慮して、また、猟師の高齢化などを背景に、射撃できる人を育成し、動物被害を少なくする目的で 2024年に完成したということです。面白い施設でした。敷地内には、いくつか射撃場はありますが、射撃の音を、吸収する意味合いでも外壁に木材を使用した木造建築物としています。もともと敷地は谷であった所を埋めて、射撃場としているので、管理棟の地盤は、柱状改良をして、地中梁のあるベタ基礎としています。
外観

北向きの外観です。天窓が存在している方向が東になります。
在来木造建築物で、延床893m2の建物です。高さ9.88mで、軒の出が2mある平屋建ての建物です。
兵庫県産材の木材を98%利用しているようです。2%は 構造用合板が 県産材に対応していなかったということです。
材種は、ほとんど杉でした。土台だけ檜を使っているようです。大径材の使用は、吹き抜けの柱のみで、今後の課題のようです。
屋根は 切妻と寄棟で、山の原風景を残すというイメージで設計されたようです。

南側の外観です。バックヤードになります。

バックヤードです。屋根は耐久性を考えて金属サイディングとし、壁は、キシラデコール3階塗りの杉羽目板でした。

軒の出が2mあるため、一度90角の垂木をだして、それを繋ぎ材でまとめ、その上に軒をはっていますが、その裏にまた45角の垂木をだしているようです。見えている垂木が、お寺の桔木のような役割をしています。

よく見ると軒裏に穴があると思いますが、ここから通気をして棟換気するようです。

屋根から落ちた水が跳ねて、外壁にとび、外壁材をいためないようにインターロッキングを設けて、排水処理をしていました。

配置図です。今回建物は、この管理棟になります。
エントランスホール

高さ9mの吹抜と 中心に配置してある 240mm角の柱が印象的でした。
上部天窓は、夏場窓をあけて空調し、いい風が流れるそうです。

真ん中をツリー構造とし、枝の材は、柱とピンでとめているようです。屋根の荷重を支えているだけの柱になるかと思います。

建物は、この吹き抜け部分で 東西に二つに分かれます。500m2をこえると、準耐火建築物にする必要があるため、吹抜けを挟んで防火壁を設け、面積区画していました。非常に分厚い防火壁となっています。
会議室

我々が講義をうけた会議室です。このトラスの勾配が屋根勾配になっていました。


トラス部分をついでいます。今回の 材は、4m材と6m材をつかって設計しているようです。一見して、梁のせいが細いなと思ったのですが、どうやら、TAPOSという兵庫県の研究所から発明された仕口をつかって、梁せいが小さくできる工夫をしているようです。

仕口の形状がV字になっており、上からの力が均等に流れるため、従来の仕口形状に比べて梁せいを小さくできるものということです。

 木造架構が面白いいい会議室になっていました。
木造架構が面白いいい会議室になっていました。
木造建築物の設計の注意点
①構造材は割れる(柱 梁)
背割れを予め入れるかどうかは、意匠上の問題点になります。
②仕上げ材はそる(壁板)

この室内仕上げ材は、3回ほどやりかえているようです。室内空調の具合含め注意が必要になります。
③木は腐る(外壁材)
今回は、2mの軒を出して、地面はインターロッキングを設けることで、外壁に雨がかからないように配慮した設計としています。
④木は色あせる(内外とも 紫外線)
屋根は今回は、ガルバリウム鋼板で設計ということです。
⑤ グリッドは910mm
この建物のグリッドを1000mmにして、設計したため、既製品がなく、かなり苦労して、多少のコストアップにつながったとのことでした。できるだけ910mmグリッドで設計するのがよいようです。
⑥柔らかく傷つきやすい。
その他

猟師がとった動物を 料理するところです。

動物の加工場です。なかなか面白いところを見れました。




射撃場です。面白いところでした。